相続事業承継設計|西口末和税理士事務所|税務・会計・経営・起業をサポート
- HOME
- 相続事業承継設計|西口末和税理士事務所|税務・会計・経営・起業をサポート
任意後見制度の概要と活用方法
従来の禁治産・準禁治産制度に代わり、成年後見制度が施行されてから10年が経過した。制度の認知度が上がるにつれて利用者が増加し、そのなかでも任意後見契約の年間登記件数は、初年度の655件から平成21年には7809件と12倍に増えた。今回は、あらためて任意後見制度の概要を確認するとともに、活用方法について解説する。
法定後見と任意後見の関係
「成年後見制度」は、認知症などにより判断能力が不十分な人の行為能力を制限し、法律行為のサポートを行う保護者をつけることで本人の権利を守る制度である。成年後見制度は、次の2つの類型に分けられる。
(1)法定後見
すでに判断能力が低下した人について、家庭裁判所の審判によって保護者が決められる。判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3つの類型があり、支援内容もそれぞれ異なる。
(2)任意後見
まだ判断能力が十分ある間に、本人が将来後見人となってほしい相手(任意後見受任者という)を選び、支援してもらう内容を決めて契約を結ぶ。
法定後見では、誰が後見人になるのか実際に選任されるまでわからないが、任意後見では事前に本人の意思で決められるのが大きな違いだ。
任意後見契約の内容
任意後見契約を結ぶと、将来実際に判断能力が低下したときに、後見人が様々な事務手続きや契約を代理することになる。内容は、「財産管理」と「身上監護」の2つに分けられる。
(1)財産管理
金融機関との取引や不動産の管理・売却など、財産に関係する手続きや契約について代理できる(図表1参照)。
任意後見は法定後見と異なり、法律上は任意後見人に売買契約等の取消権限がないとされるが、契約書の代理権目録に「契約の変更、解除を含む」などの文言を入れることはできる。実務上は、任意後見人が本人から通帳やカードを預かって買い物ができないようにしたり、本人と業者間の契約の取り消しを後見人がサポートすることでも対応可能だ。
(2)身上監護
医療・介護、施設入所のための手続き、要介護認定の申請など、本人の心身を守るために必要な手続きや契約について任意後見人が代理できる。
注意したいのは、任意後見人はあくまでも本人が最適な治療や介護を受けるためのサポート体制を整えるだけで、実際に介護そのものを行う義務があるわけではないことだ。また法律上、本人が重大な手術や延命措置を受けるかどうかの同意権は任意後見人にはないとされる。
任意後見契約が役立つ場面
(1)財産を守れる
悪徳商法の被害を防いだり、親族などが勝手に預貯金を引き出したり不動産を売却することを防げる。必要があれば、弁護士に訴訟委任することも可能である。
また、たとえ本人が判断能力のあるうちに遺言書を作成していても、相続発生時に財産が残っていなくては意味がない。家族にとっては、任意後見人をつけることで将来相続すべき財産を守れるという面もある。
(2)介護費用を調達しやすい
入院や介護でまとまったお金が必要になったとき、任意後見人が不動産の売却や定期預金の解約を行えるのですみやかに資金調達できる。
(3)現在の生活を維持できる
任意後見人が財産を管理して生活費の支払いを代理することで、電気を止められたり税金の滞納で自宅を差し押さえられるといった事態を避けられる。また、任意後見人には本人がきちんと介護を受けているかなどの生活状況に注意を払う義務がある。
(4)相続発生に対処できる
本人の親族が死亡して相続が発生した場合に、任意後見人が代わりに遺産分割協議に参加したり、相続放棄や限定承認できるため、本人が知らぬ間に借金を背負わされるといった事態を避けられる。
任意後見制度を利用するには
(1)受任者を決定する
任意後見の受任者は、欠格事由に該当しなければ誰でもなれる。司法書士などの専門家(FPも含む)、法人や複数人も可能だ。報酬は決めても、無報酬でもかまわない。
(2)契約を結ぶ
任意後見契約は法律により、公正証書での締結が義務づけられている。その後、公証役場の公証人の嘱託により、法務局で契約内容が登記される。
(3)契約の発効
契約を結んでも、すぐに効力が生じるわけではない。将来、本人が認知症などにより判断能力が低下した時点で、受任者などの申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、選任されたときに契約の効力が生じる。同時に、受任者は任意後見人として活動を開始する。
(4)契約の終了
当事者の死亡、契約の解除・解任、受任者の判断能力が低下して後見開始の審判を受けた、などの事由により終了する。
他制度との併用も
現時点では判断能力に問題はないが、身体機能が低下していたり、将来身体不自由になった場合に備えたいという人は、任意後見契約と同時に、日常的な事務手続きについての委任契約(財産管理等の委任契約)を結ぶことも考えられる。内容は任意後見契約と同様だが、本人の判断能力が十分なうちに契約が発効するという違いがある。
このようにすれば、判断能力に問題がないうちから受任者が財産管理を行うことで、将来判断能力が低下したときは任意後見にスムーズに移行できるという利点がある(図表2参照)。このように2つの契約を結ぶことを「移行型」というのに対して、任意後見契約だけを結ぶことを「将来型」という。
ただ、委任契約の場合は任意後見契約と違って公的な監督者がつかないため、受任者による代理権の乱用を防ぐために、代理権の内容を限定するなどの対策をすべきだろう。
FPが高齢者の財産管理や将来の遺産相続についてプランを立てる際に、これらの契約と遺言書を組み合わせて活用することも考えられる。例えば、親と別居している子どもが、親と同居しているきょうだい(兄弟姉妹)に親の世話を頼む代わりに、将来相続放棄をしてもかまわないと考えているような場合に、親が同居中の子どもと移行型の任意後見契約を結び、その子に財産の大半を相続させるという内容の遺言書を作成したうえで、別居する子が遺留分放棄の手続きをとることが考えられる。これらの制度を活用することで、相談者の将来の不確定要素を減らし、スムーズな相続が実現されることが期待できる。
図表2■移行型の任意後見契約のイメージ
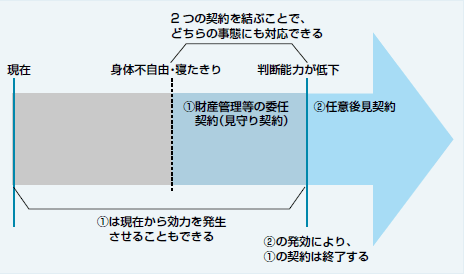
(FPジャーナル2010.10月号より抜粋)